新刊『「忙しいのは当たり前」への挑戦』のあとがき
みなさん、こんにちは!このブログもとっても不定期更新となっておりますが、お知らせです。新刊が出ました。正確に言うと、今月2冊出ます。
じゃじゃん、第一弾は、『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』です。
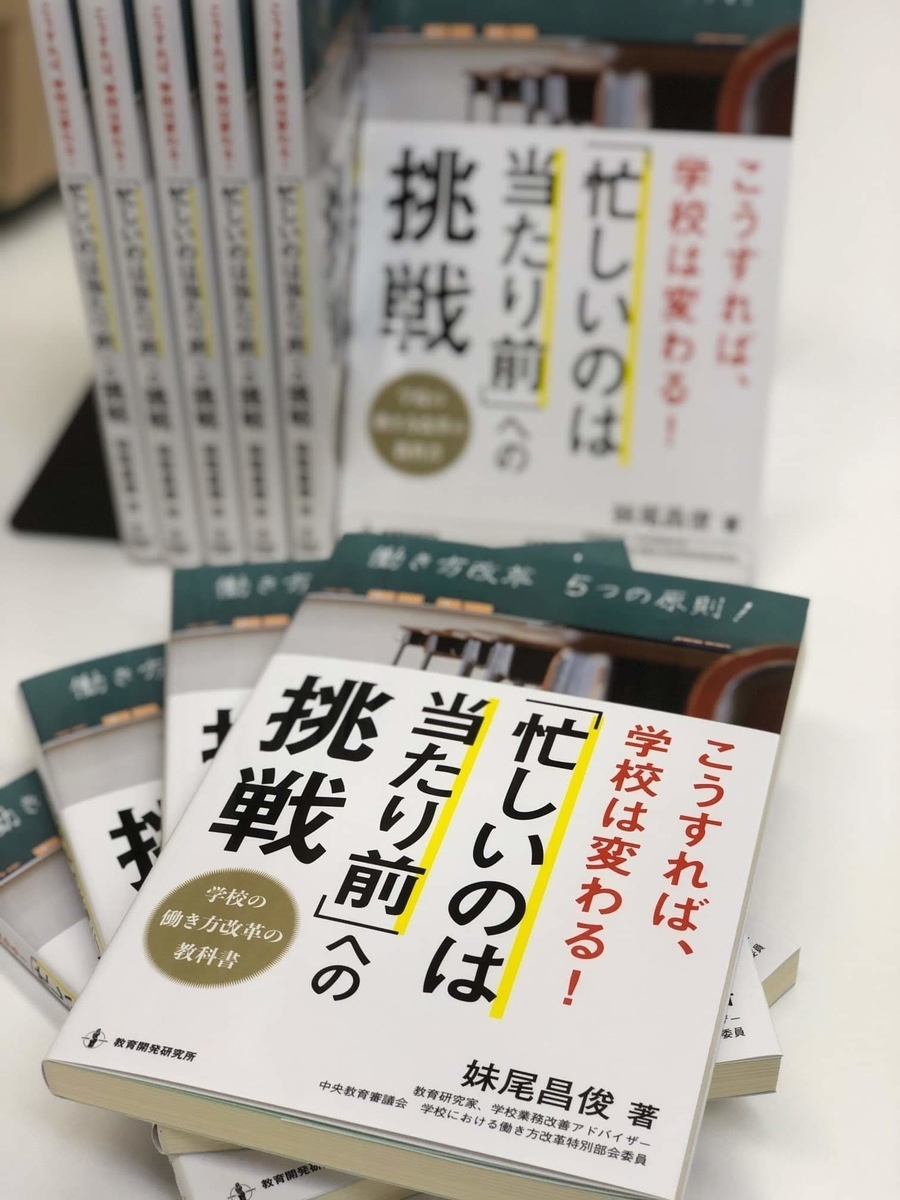
学校の働き方改革や業務改善について、みなさんの学校では進んでいますか?
- 「いやー、掛け声だけだよね」というところ。
- 「早く帰れ」とだけ言われたって、仕事が減らないんじゃ、どうしようもないじゃない、という声。
- 部活動や行事をめぐっては、いろんな意見が職員のなかでも、保護者のあいだでもあって、どうしたらよいか困っているという学校。
などありますよね。
本書では、こうしたみなさんのギモンや悩みを踏まえながら、陥りがちなまちがい(失敗と言うと言い過ぎですが)を避けて、効果のある働き方見直しを進めるための5原則を、とにかく具体的に解説しています。
★出版記念のトークセッション(セミナー)もやります。7月6日夕方@八重洲ブックセンター。
校則ゼロにしたことで有名な世田谷区立桜丘中学校の西郷校長先生をゲストに、学校は、教師は、真にどんなことに時間とエネルギーをさいていくべきか、深掘りますよ~。
(詳細、お申し込みはこちら)
https://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/camp/talkevent.html
★★★
きょうは、このブログで、本書のあとがきを公開します。
”あとがき”って最後に読むものじゃないか?と思われている方、
はい、ふつうはそうなんですが、あとがきから読むという読書法もあります。あとがきに、その人が言いたいことがまとまっているという場合もありますし。あるいは、執筆の動機とか。
なので、もしよかったらご参考になればと思い、アップしてみました。
・・・あとがき・・・
「なぜ、妹尾さんは、働き方改革や学校改善に、これほどアツく取り組んでいるんですか?」
各地で講演・研修などをしていると、時よりこんな質問をいただきます。理由は、大きなところでは3つでしょうか。
ひとつは、熱心な先生の過労死に接したからです。2011年には堺市立中学校に勤務する26歳の前田大仁さんが亡くなっています。教科指導も部活動も熱心で、生徒からもとても慕われていた、2年目の若すぎる過労死でした。
「主人が亡くなったときは10歳だった次女が、もう20歳。これからはお父さんのいない月日のほうが長くなります。」一昨年そう話してくださったのは、工藤祥子さん。横浜市の中学校教師(保健体育)だった義男さんは修学旅行の引率後に体調が悪化し、亡くなりました。40歳。前任校では⽣徒指導専任と学年主任を兼務し、かつ授業数も規定の上限より多く、進路指導やサッカー部の顧問も担うなど、とても“専任”とは言えない多重な多忙のなかにいました。
いくら児童生徒思いだからといって、命を縮めるほどの多種で大量の仕事を強いるべきではないし、このような献身的な教師の過労死は二度と起きてほしくない。そう多くの人が共感されると思います。ですが、上記も含め、教師の過労死や過労自殺があっても、検証報告書らしいものはなにも出ないし、再発防止に向けた施策が自治体等を越えて共有されたという形跡もありません。そして、似た事案がそのあとも実際に起きています。
これはどう考えてもオカシイ。そう感じたのが、ぼくが、教師経験もなく、教育行政関係者でもない、ヨソモノであるにもかかわらず、働き方改革に本格的に取り組むようになったきっかけです。
ふたつ目は、全国各地にとてもいい先生が多いことを知っているからです。ぼくが中高生だった頃の恩師もそうでしたし、仕事を通じて、ありがたいことに、ステキな先生たちと多く出会いました。ママ友、パパ友でもある、同じ年の小学校教諭は、三人の娘さんを寝かしつけたあと、朝4時に起きて授業準備などをこなしています。ですが、ひとつ目と重なりますが、こうした友人たちも“死と隣り合わせ”の現場にいるのです。これはなんとかしたい、自分のできることはしたい、という気持ちで活動しています。
3つ目は、約3年前からぼく自身が脱サラして、比較的自由がきく仕事にライフシフトをして挑戦中であることも影響しています。まだまだ試行錯誤なところはありますが、自分の好きなこと、真に重要と思うことに人生の多くの時間を振り向けられるようになりました。間違いなく、自分や家族の幸福度は高まったと思います。
ついでに申し上げると、働き方改革の成果指標は、時間外月80時間(あるいは45時間)超えの割合とか、残業時間の平均値などとしている自治体が多いのですが、それらに依拠しすぎるのは考えものです。そうした数字のモニタリングは重要ですが、本質的には何がもっと大事かを繰り返し問い直し、共有していかないと、「残業時間が減りさえすればいいのね」と短絡的に考える人も忙しい現場では多くいます。原則月45時間・年間360時間というガイドラインができて、その懸念は強まる一方です。既に虚偽申告や過少申告が横行している地域もあります。
「教職員が幸せを感じて、イキイキと働けているか」どうか、「この仕事を自分の子どもや甥っ子、姪っ子らに自信をもって勧めたいか」、「育児や介護、病気を抱えても無理なく続けられると思うか」、「自分のクリエイティビティや思考力を高める時間も取れているか」といった指標でもいいのではないかと思います。本書で「Why働き方改革?」という点を考えてきたこと(第2章)とも重なる話です。
話を戻しますね。エラそうなことを言うつもりはないのですが、ぼく自身の生き方をとおして、出口治明さんの提案する「本、旅、人」から学び続ける人生は、とても面白いと実感しています(第5章)。
時間どろぼうの“灰色の男たち”に人生をゆだねるのではなく、自分の時間を取り戻すこと。あれもこれもという発想ではなく、ある程度真に重要なことを選択した上で、時間対効果を高めて仕事を進めることは、自分とまわりの幸せにもつながります。このことは、自信をもっておススメできます。
教師の仕事の多くは、授業準備などを典型として、どこまでいっても百点にならず、キリがない性質をもっていますし、プライベートでの活動や自己研鑽などと仕事を完全に区別するのは難しい場面も多くあります(専門家は無限定性、無境界性などと呼んでいます)。ぼくにとっては講演の準備や本の執筆なども似ています。映画を観ても、ディズニーランドに行っても、「これは今度研修のネタに使えるな」とか考えていますから。ですが、だからといって、どこまでもズブズブやっても、いいものはできませんし、疲れを溜めるよりは、(いいアイデアが浮かばないか、考え続けることはしながらも)リフレッシュしたり、本・旅・人などで視野を広めたりしたりしたほうが、結果的にはアウトプットはよくなると感じます。
AI時代に、子どもたちにクリエイティビティや問題解決力などが重要となっているなか、ぼくは、日本中の先生たちにもクリエイティブな時間を楽しんでほしいと感じています。
以上が、ぼくが働き方改革に本気で取り組む理由です。
How about you? みなさんはガチで取り組んでいますか?
「学校現場は絞りきった雑巾のようです。国のほうでもっと教員数を増やしてくれないと、ムリですよ。」
これも、講演などのとき、しょっちゅうお聞きします。
ぼくも、とりわけ小学校においては、教員数はもっと必要だと強く感じています。トイレに行く暇もないほど、休憩も取れないというのは人間的な労働環境とは言えません。また、教員定数の決め方は、小学校は学級担任制を前提としているため、中学校や高校と比べて著しく不利で、級外(担任をもたない人)が多く出ない計算式になっています。これでは有給休暇や病休も取りづらく、よほどしんどくなってからしか休まないという人が多くいます(自分が休むと代わりがおらず、自習等になることも多いので)。
では中高と比べて、小学校の先生がラクかと言えば、まったくそんなことはなく、「どうして雨は降るの?」、「どうして分数の割り算は逆さまに掛けるの?」という子どもたちの素朴な疑問に答えていく仕事です。しかも8教科、9教科など準備。加えて、家庭の貧困問題や発達障がい、外国にゆかりのある子等も増えて、福祉的な配慮やきめ細かな教育的支援が必要な子も大勢います。さらには、新採で3日目、4日目から学級担任をする人がほとんどです。
財政制約が厳しいことも承知していますが、小学校の教員定数の決め方は根本から見直すべきだと思っています。
ですが、同時に、とても気になることがあります。国がやってくれないと、と言う人の多くには、「教員数が増えないうちは、学校や市区町村(または都道府県等の)単位では、たいしたことはできない」と思い込んでいるか、あきらめているふしがあります。本書の各章で述べたとおり、そんなことはなく、学校や地域で進めていけることも多いです。絞りきった雑巾のようという気持ちはわかりますし、これまで学校現場にビルド&ビルドで負担を増やし続けてきた文科省や教育委員会は猛省してほしいと思いますが、主体性も問題解決力もない態度を教師が続けていては、多少教員数が増えても、業務量や残業はたいして減らない事態になるでしょう。
また、何かしら働き方改革や業務改善に着手しても、いわば、あさってな方向に動いていたり、道に迷ったりしている学校も少なくないことをぼくは見てきました。冒頭で述べた、5つの大まちがいはその典型例です。
そこで、本書では、働き方改革を進める上で“地図”や“ガイド役”となりたいと考え、5つの原則とそれに紐付く具体策を提案しました。この5原則は、特段派手ではないし、読者のみなさんにとっては「当たり前」のことを述べているだけと感じるかもしれません。しかし、「忙しいのは当たり前」という学校を変えていくためには、「当たり前」に見えることを真面目に着実に進ちょくさせていくしかないのです。ぜひ各校等においては、「Why 働き方改革?」という理念、目標を十二分に共有したうえで、多忙の内訳を分析して、重点的に取り組むべきことを決め、工程表にするなどして、具体的に落とし込んでほしいと思います。
本書の内容には、国の審議会や各実践地域・学校で伺ったことや議論したこと、教育関係者らと楽しく飲みながら考えたこと、ぼくの趣味や育児経験などがふんだんに活かされています。紙面の関係上、個人名はあげませんが、たくさんの人のおかげです。今後も進化・深化させたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
本書が「忙しいのは当たり前」という学校の慣性の法則へ、
挑戦する一助となりますように。
講演で関西に向かう新幹線のなかで 2019年5月
妹尾昌俊
・・・以上お知らせでした。写真は最近の著者です・・・
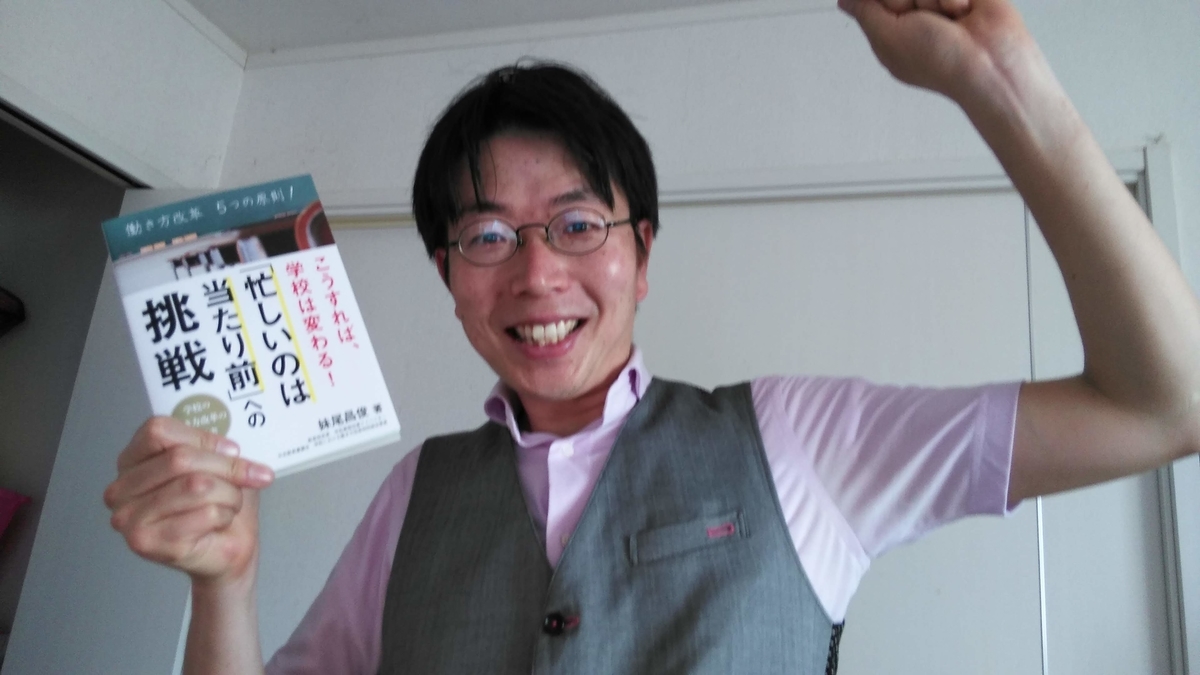
★Amazonの学校運営で1位となりました★
予約、購入いただいたみなさん、ありがとうございます。忌憚なくご感想やレビューなどよろしくお願いします。ほかの既刊も引き続き応援よろしくお願いします。
多動な2018年!2019年もそうかな
このブログもずっと更新をさぼっておりましたが、妹尾はいたって元気です。この1年は、ちょうど1年前の1月1日だけ高熱を出してしんどかったのですが、幸い、ほかは大病なく、まあ、けっこう太ったかなということ以外は、大丈夫でした。
2018年は、漢字で一言で言うと、「多動」だったかなと思います。
ホリエモンこと堀江さんが『多動力』という本を出していますが、ぼくの場合も、とてもラッキーなことに、あちこちに顔を出しながら、自分の好きなことを進めることができたかなと思います。これは2019年も大事にしたいと思います。
よくライフワークとライスワークはちがう、と言われます。好きなことばかりやっていても、なかなか生活できないよ(ライスワークにはならない)とか。
ぼくはこの話を、前職の会社勤めをしていたときに悶々としながら過ごしていました。とても鍛えられたよい職場でしたが、自分の好きなテーマでの社会課題解決に時間をもっと割きたいということで、2年半前に退職し独立。そのあとは、すぐには仕事はあったわけではなく、しっかり見通しもないまま見切り発車でしたね。かなりヒマなときも多くて、その当時、生活を支えてくれていた妻からは「あんた、週2も海(SUP)に行って、遊びすぎ」と言われていたほどです。。。

いろいろよいご縁もあって、この1年は、全国各地を訪問して、学校づくりを応援、伴走することができました。いま自分のスケジュールを見返しましたが、風邪をひかずにほんとよかったです。
まだまだスポット的なもの(1回講演に行ったきりなど)が多くて、もっと継続的にお手伝いできるところも増やしたいなと思います(2018年度は山口県教育センターや四日市市教育委員会、横浜市教育委員会など、継続的にサポートしています。)。以前よりは、だいぶライフワークとライスワークも近づいてきた感触はあります。
ちょうど1年前にYahoo!ニュース個人というサイトで、働き方改革や部活動問題をはじめとして、解説しています。このブログの更新は滞りましたが、よかったら、Yahoo!のほうもご覧ください。また、FacebookやTwitterをフォローいただければ、関連情報は毎日のように発信しています。
今年は本も単著で1冊出せました!(共著も少し。)『先生がつぶれる学校、先生がいきる学校』はずっとあたためてきた内容で、モチベーションマネジメントと長時間労働是正をメインに扱っています。実例も含めて、具体的な事例をもとに、当事者意識をもって考えられるケースメソッド本になっています。
Amazonで著者ページもできました。↓
本や記事を書くのは大好きなので、2019年も頑張りたいと思っています。いま構想中と執筆途中のが2つあります。
中教審の働き方改革部会、スポーツ庁と文化庁での部活動ガイドライン検討会議など、国の審議会にも、今年はたくさん出ました。資料を出したり、会議中に遠慮なく、思い切った提案をしたり。ともかく真剣勝負でのぞみました。この姿勢は娘たちの小学校のPTAの会議などでもいっしょです。
講演をしたり、本や記事を出したり、国の審議会に出たりすることは、それら自体が目的ではありません。拙著『思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校』の最初に書いた次のこと、気持ちは、今年も2019年も大事にしたいと思っています。
すばらしいアイデアも、読んだり、聞いたり、考えたり、書いたりするだけではだめだ。(※)
この一節に出会ったとき、ドキッとしました。わたしはこれまで10年以上大手シンクタンクの研究員として、また2016年に独立したあとは教職員向けの研修講師として、いわば“すばらしいアイデア”を売る、広めることを仕事にしてきたからです。
なぜドキッとしたのか。それは、100枚近いパワーポイントをつくって理路整然とプレゼンしても、あるいは一度に数百人をアツくする講演ができたとしても、相手が動かなければ、学校も、その先の子どもたちも変わらないからです。「今日はいい話が聞けたなあ」、「とても満足した」とは言ってもらえるし、アンケートでも多くがそう答えてくれるのですが、それだけでは不十分です。わたしはカウンセラーでも、落語家でもないのですから。
(※)ジェフリー・フェファー他(2014)『なぜ、わかっていても実行できないのか―知識を行動に変えるマネジメント』(長谷川喜一郎・菅田絢子訳)、日本経済新聞出版社、p.3
2018年も本当にたくさんの方に支えていただき、あるいは刺激的なアイデアなどを交換でき、ありがとうございました。2019年もあちこちで、笑いをとりながら、行動につながるきっかけをどんどんつくっていきますので、どうぞよろしくお願いします。
連絡先:senoom879あっとgmail.com
またはFacebookメッセンジャーかTwitterDMでお願いします。
※あっとは@にしてください。
※たまに勝手に迷惑メールに自動的に振り分けられることがあり、気づかない時があります。
部活は学校の業務なのか??
中教審での学校の働き方改革についての議論がひとつの山場を迎えています。もうすぐ中教審の中間まとめも確定版になる予定です。この中間まとめでは、これまで学校が担ってきた仕事や、教師がやって当たり前だった業務について、
- 必ずしも学校や教師が担う必要がないこともありますよ
- 実際、法令上も縛りは少ないですよ(=教委や学校ごとの裁量ですよ)
- 今後はこういう方針で考え直してはいかがでしょうか
といった内容を多く含んでいます。

たとえば、運動会の準備や当日に何時間くらいかけるか、とか、掃除の時間は毎日設けるかなど。これらは学校裁量です。文科省は、法律や学習指導要領などでほとんど規制しておりません。そういうことも、言うまでもないことも多いかもしれませんけれど、中教審の審議のなかでひとつひとつ確認していきました。
国が大いに反省しないといけないことや支援が必要なことも多いのは確かです。一方で、学校の裁量や前例、慣習のなかで仕事を増やしてきた部分への反省も同時に必要だと思います。
中教審の議論についての報道では、教師の残業時間に上限目標を定めることを検討するとか、部活のあり方についての話題が多く見られます。それらもすごく大事なことですが、学校の働き方改革は、それらだけでは決してないです。
ページ数がそれなりにありますから、忙しい学校現場の先生たちや、教育行政の担当の方にすべて入念に読め、と言うのは気がひけますが、ぜひどこかで、ざっとでもご覧いただければ、ぼくの言っていることがご理解いただけると思います。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/index.htm
さて、この中間まとめの当初案で、ネット上等で大きく話題になったことがあります。それは、学校における部活動の位置づけについてです。11月28日の当初案では、「部活動については学校の業務と位置付けられ,現状では,教師が担わざるを得ない状況である」との表現となっていました。これが、先日の12月12日バージョンでは、同じ箇所について「各学校が部活動を設置・運営することは法令上の義務とはされていないが,現状では,ほとんどの中学校及び高等学校において部活動が設置され,教師が顧問を担わざるを得ない状況である。」との修正がなされました。
ただし、「部活動については,学校の判断により実施しない場合もあり得るが,実施する場合には,学校教育の一環であることから,学校の業務として行うこととなる。」との言及は別の箇所で残っています。

こうした部活動の位置づけについて、現教審(現職教員等から構成された会議)などをリードされている先生たちのなかには、「部活を学校の業務として位置づけるのは、怒りすら感じる。これが大義名分となって、校長のなかには、顧問をやりたくない人にも押しつけようとする。そこを危惧する」とおっしゃっています。
この心配は、これまで、少なくない学校で、部活動顧問を強要してきた歴史からすると、しごくまっとうな反応だと思います。ぼくもそこは心配だったので、次の意見出しをしました。
「部活動については学校の業務と位置づけられ」と書かれていますが、誤解を招く表現であり、修正したほうがよいと思います。典型的な誤解は、学校がやらねばならない業務、必須の業務とこれを読んで解釈する人がいます。
指導要領上、教育課程外なのですし、生徒の自主的活動なのですから、学校が部活動を行うことはどこも強制していないことを、この中間まとめでも確認することが必要だと思います。
ぼくの意見が少しは反映されたのか、あるいはネット等での現職の先生たちの叫びが影響したのかは知りませんが、修正案では、部活は必須の義務ではない、ということが確認される文言となりました。でも、「部活=必須じゃないけど、やるなら学校業務だよ」という位置づけは明記されたわけです。
これは、いったい、どういう意味なのでしょうか?
ややこしいのですが、「業務」という言葉の定義を確認しないと、誤解を招きます。
「学校の業務=学校が担わねばならない義務的なこと、必須のこと」と定義するなら、部活は学校の業務ではありません。しかし、中教審の中間まとめでは、この定義は採用していません。部会長や事務局にも確認しないといけませんので、あくまでも妹尾の個人的な見立てですが、おそらく、「学校の業務=学校の責任下で行う仕事(ただし、必須かどうかは問わない)」という意味でこの用語を使っています。
部活は、指導要領上、教育課程外ですので、中教審の中間まとめで確認するまでもないことですが、もともと、必須や義務ではありません。生徒の自主的な活動なのですから、やりたい生徒が一定数いて、それに校長が賛同すれば、学校の責任と裁量で設置するものです。仮に必須のこととするなら、教育課程内に位置づけないと、いけません。
(写真:今日は新潟に行ってました。教頭研修です。)

当然、顧問をすることを校長や教育委員会が強制することはできません。強制なら自主的な活動とはなりませんし、教育課程外なのですし、時間外勤務を認める超勤4項目(修学旅行や緊急時等に時間外勤務しろと命令できる項目)に部活は入っておりませんので。百歩ゆずって、勤務時間内なら校長が顧問やれと命令することは不可能ではありませんが。。。実際は勤務時間外に部活をするというのは、フツーなので、勤務時間内だけ部活動しろという命令が飛んでいる学校はほとんどないと思います。
それでですね、「学校の業務=学校の責任下で行う仕事(ただし、必須かどうかは問わない)」という定義をとるならば、ある学校でこの部活は学校教育の一環としてやりましょう、と決めたものは、明白に学校の業務です。
仮にですよ、部活=学校の業務外としてしまうと、次の大きな悪影響があります。
- 生徒の事故や怪我が起きたとき、学校の責任外となってしまう。そうすると、生徒(ないし家庭)からすると、学校の責任を問えなくなるかもしれない。
- 教師が過労死したり、病気になったりしたとき、学校の業務外とされてしまうと、いわば、先生の趣味かボランティアでやっていたのね、となりますから、下手すると、公務災害(私立学校の場合は労災)と見なされないこととなってしまう。
- 土日の部活動指導には、一定時間以上は特殊勤務手当のひとつとして、部活動手当が付いている地域がほとんどだが、業務外となると、税金を支出する根拠があやしくなる。教師の趣味に公金を使うわけにはいかんでしょ?
このように、部活=学校の業務外と見なしてしまうと、不都合も多いのです。
でもですよ、いまの部活の制度が矛盾だらけなのも確かです。
学校の業務として、つまり教師の趣味じゃない活動として、職務として部活指導をやっているのに、超勤4項目には該当しないのですから。同時に、完全に教師の自発的な活動やボランティアだとは見なせないところもある。
こういう点で、部活の現状の位置づけは、非常に中途半端というか、よくわからない制度と運用となっているわけです。
だからといって、超勤4項目に部活を追加したらよい、とは、ぼくは全く思っておりません。今後のあり方はよくよく考えていかないと、今のままではおかしいことや誤解が多いのです。
引き続き、こうした点をぼくは中教審やスポーツ庁の審議会等で申し上げて、多くの方と検討していきます。
★こちらもご覧になってください。
ある学校事務職員さんと
今日は、文科省主催の学校マネジメントフォーラムというシンポジウムが神戸であって、行ってきました。事例発表への助言者ということで、ちょっとしたコメントを、遠慮なく(笑)。発表者も、聞きに来てくださった方も、みなさん、頑張られている方が多くて、とてもよい刺激になりました。
あいかわらず、久我先生@鳴門教育大学のお話はビシビシくる素晴らしいものでした。来月は、東京でもマネジメントフォーラムがありまして、ぼくも講演+事例発表へのコメントをいたします。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1394038.htm
このシンポジウムもとてもよかったですが、今日はぼくにとってすごくうれしかったことがあと、2つもあります!
ひとつは、前から行きたいなと思っていた、天空の城、竹田城に行けたことです。しかも、天候、コンディションは最高で、絶景中の絶景でした~。ぼくのフェイスブックで写真と15秒の動画をアップしています。
ほんとうに雲の上にいるような気持ちになります。昨日、兵庫県の但馬地方(但馬牛がめちゃうまです!)で事務職員研修会があって、その近くだったこともあり、ある事務職員さんに連れていっていただきました。朝6時から車を走らせていただき、ありがとうございました。

もうひとつは、闘病中のある学校事務職員さん(Mさんとします)と1年ぶりにお会いできたことです。Mさんは、以前研修会で呼んでくださった縁があり、その後もときどきメールなどでやりとりが続いています。
ちょうど1年前に研修会があり、そのときは普段通りだったのですが、その後、病気が見つかり、いまは休職されています。
今日は早朝竹田城に行って、午後は文科省のフォーラムに行って、そのあいだに1時間弱ほどだけですが、ちょっとだけお見舞いがてらお話できました。
薬の副作用もあるので、おそらくたいへんつらい思いもなさっているのでしょうが、「わたしが休んで、臨時の職員さんが来てくれているんですけど、何かと心配で」と、職場の心配をされているのが印象的でした。また、学校事務職員の処遇や職場での立場がまだまだ弱いところも多いことについて、「わたしらの(ベテラン世代)がしっかり仕事してアピールしてこなれなかったせいかも」、ともおっしゃっていました。
やはり、このあたりが職人気質と言いますか、仕事への誇りを感じるところです。
とても冷たく、ドライに言ってしまえば、たいていの職場は、企業であれ、行政や学校であれ、その人がいなくても、残念ながら職場は回っていくのです。代替要員が来ますし。あのスティーブジョブズだって、いなくなったあともアップル社はちゃんと続いています(かつてのような革新性を続けられているかの議論はあるとしても)。
とはいえ、同時に、使命感と言いますか、もっと職場をよくしたい、とか、わたしも世の中にちょっとでも役立ちたい、という気持ちはとても大切だと思います。重い病気で大変だろうのに、仕事や学校のことをよく気にかけておられるMさんの姿を見て、うまく言えませんが、どうでもいい、休めてよかったと思えるような仕事ではなく、やれてよかった、やりがいがある、と思える仕事をぼくも続けたいなと思いました。
はなはだ月並みな言い方かもしれませんが、人間、無理を重ねてはいけませんが、できるときに、できることをする、自分の力は、大海に一滴を落とすほどの、ほんの小さな影響かもしれないけど、何かの行動をしていくということが大切だなと思います。
帰りぎわに「会いに来てくれて元気がもらえた」とMさんに言ってもらえたのが、うれしかったです。ほんのちょっとした行動だったのでしょうが。もう少し元気になったら竹田城めぐりをご一緒したいです。

世論の変化、学校は大丈夫か?
福井の池田中の生徒の自殺は本当に悔やまれますが、これで学校教育への世論が大きく変わりつつあるように思います。
それは教師批判、あるいは、学校は大丈夫かという疑問が増幅している、ということ。
少し前までは、学校の多忙化を大きな問題とするときに、「先生たち、朝早くから夜遅くまで頑張ってくれているね」といった雰囲気が保護者や世論にも少しずつ増えてきていると思いました。
このことは、調査データの類いで確認できているわけではないので、慎重に検証する必要はありますが、PTA役員会でもそう感じたし(まあ、PTA役員は熱心な親なのでバイアスはかかっているけれども)、あちこち講演してまわって全国いろんな教職員の声から肌感覚で感じました。
しかし、これが今、大きく変わりつつあります。

池田中について調査委員会報告書(概要版)では、
本生徒は、担任、副担任の双方から厳しい指導叱責を受けるという逃げ場のない状況に置かれ、追い詰められた。
・・・
担任、副担任の厳しい指導叱責に晒され続けた本生徒は、孤立感、絶望感を深め、遂に自死するに至った。
と明記されています。教師による”指導”(ぼくはこれを指導と呼ぶことには反対ですが)が生徒の死につながったということです。また、この生徒の母親の手記ではこう書かれています(福井新聞2017年10月18日)
子供を教える立場にありながら、自らが犯した、重大な責任に気付かず、悪いとも思わず、反省もせず…。今だに、子供達を教える立場にいる人達に、怒りと悲しみを感じています。
教員と生徒の間の為、叱責という言葉で表現されてはいるものの、私達遺族は、叱責ではなく「教員による陰険なイジメであった」と理解しています。叱責だけではなく、○○を罵倒するような発言、人権を侵害するような発言も、多々あった、と聞いています。
この母親の気持ちに共感する人は、ぼくを含めて多いと思います。
加えて、先日もいじめが増加していることが報じられました。いじめはある時点で定義が拡大したし、どこまでをいじめとするか難しい問題がつきまとうので、単純に過去とは比較しにくい統計のひとつなのですが、そうとばかりは言っていられず、深刻な問題が続いているのは事実です。
こうした報道に接していると、先生たち、少々夜遅くまで仕事している人が多くても、子どものいじめや人権を守れないで、何しているの?
といった反応をする人がいても、不思議ではないと思います。
もちろん、池田中の担任、副担任のような態度をとる先生が全国に多くいるわけでないでしょう。しかし、本当に「学校は大丈夫か?」という疑念がいま増幅しているように感じます。
そんなことを感じていていた折に、昨日はこんな報道がありました。
www.asahi.com引用します。
生徒の母親は2015年4月の入学時、生徒の髪が生まれつき茶色いことを学校側に説明。黒染めを強要しないよう求めた。しかし教諭らは、染色や脱色を禁じる「生徒心得」を理由に、黒く染めるよう指導した。「生来的に金髪の外国人留学生でも、規則では黒染めをさせることになる」とも述べたという。
生徒は黒染めに応じていたが、色が戻るたびに染め直すよう指示され、2年次の16年9月には黒染めが不十分だとして授業への出席を禁じられた。翌10月の修学旅行への参加も認められず、現在も不登校が続いているという。
これを読むと、明らかに行き過ぎた”指導”であると多くの人が感じるでしょう。
そもそも、頭髪”指導”の必要性と合理性はどこまであるのか疑問です。
おそらく、頭髪”指導”が行われているのは、次のような考え方があるためと推察します。
髪染めてる子
⇒学習や生活習慣の乱れのあらわれ
⇒放置しておくと他の生徒にも伝染する
⇒早めになおさせる
ほんまでっか?的なロジックです。髪を染めている子がみんな勉強をないがしろにしたり、他の生徒に迷惑をかけたりしているわけではないでしょう。また、学習や生活習慣の乱れを問題視するのであれば、それは、頭髪”指導”では解決できず、授業についていけるように支援することが本筋なはずです(このあたりの話は拙著にも書いています)。
さらに、本件ではもともと地毛の話なので、この論法では正当化できません。つまり、目的の合理性から言って、かなりあやしい”指導”です。
ひとつ必要性がまだ正当化されうるのは、大学進学や就職の面接のときに茶髪だとイメージ悪いから、高校生活のときから黒髪にしとく、という話です。外国にゆかりのある人もこれだけ増えているわけで、社会の見方も今後変わっていく必要があるのは確かです。また、仮にこの理由があるとしても、個々人の選択制にしたらよいのではないか、という疑問も残ります。
加えて、修学旅行に行かせない、不登校にさせるほど”指導”するというのは、手段の合理性から言ってもおかしい話です。そこまでしなくても、と常識的には思いますよね?
それで、こういう事例も見ていると、やはり、「学校は大丈夫か?」と思ってしまいます。
- なんのための学校教育なのか?
- なんのために教師をしているのか?
- 学校のローカルルールの必要性や合理性をちゃんと考えないで押しつけて、それで本当に思考力や判断力を養う教育ができるのか?
こうした疑問に真剣に向き合ってほしいと思います。
ぼくは、全国各地で多くの先生たちがまじめに、一生懸命に仕事をしているのをよく知っています。子どもへのケアもすごく丁寧で、それがゆえに多忙になっている現実を知っています。しかし、同時に、今のままで大丈夫か、もっとよく考えよう、もっと同僚と協力しながら”○○指導”について見つめ直してみよう、とも感じています。
先生たちが頼りない、という世論が強くなれば、教員免許更新制が導入されたときと同様に、さらなる負担が学校や教育委員会に課されるのでは、と心配します。すでにコンプライアンス研修などを強化しようする動きはあります。
国や教育委員会が見直すべきことも多いですが、各学校でも自浄といいますか、自分たちの教育をしっかり見つめ直してほしいと思います。
池田中のこと、いじめ増加の報道、大阪の頭髪指導のこと。教職員の方や教育委員会の方は、よそで起きたことと脇に置くのではなく、真剣にとらえてほしいと思います。今、どうするか考えて動いておかないと、世論はどんどん学校に冷たくなるのでは、と心配します。
★お知らせ 今度かかわっているNPOで学校の働き方改革をテーマに、具体的な取組を立案するフォーラムを開催します。
正直申し上げて、登壇者、参加予定者ともに、すごく多彩でほかでは聞けない話がたくさん出てくると思います。ワークショップもやりますよ~。
※参加申し込みはウェブまたはメールで。

★妹尾の本はAmazon在庫切れが続いておりましたが、復活しました。
多くの方にお読みいただき、ありがとうございます。

思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校―変わる学校、変わらない学校 実践編【I】
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2017/09/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

変わる学校、変わらない学校―学校マネジメントの成功と失敗の分かれ道
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2015/10/19
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
★参考記事
校長先生!20時には帰ろう運動ではダメです!
みなさん、こんにちは。連日あちこちに講演、研修しております。
先日ある校長が、「職員には20時には帰るように呼びかけてます」とおっしゃっていました。この学校はいろいろよく頑張っている学校です。地域の伝統校であり、それがよくも悪くも仕事を増やしている部分もあるようです。一生懸命なのはよいことですが、「この呼びかけではダメです」とぼくは申し上げました。
理由はシンプルです。
学校の先生は、朝早い人が多いです。おそらく7:30前後には来ている人も多いでしょう。そうすると、19:30まで働いたとすると、12時間労働です。休憩時間は控除する必要がありますが、小中学校は実質まともな休憩は取れていないことが多いです。
別のある市のアンケート調査によると、完全な休憩時間をとれている(つまり、業務はおこなっていない)教員は小中ともに1%でした。多少とっていたとしても、この時点で、残業時間は約4時間ですね(12時間ー7時間45分なので)。
1か月の平日は何日あるでしょうか。だいたい20日~23日くらいです。
約4時間×約20日=約80時間/月の残業。これですでに過労死ライン上です。
しかも、次のものを加える必要があります。
・自宅残業
・土日の出勤
土日も部活指導に出かけたり、休日に静かな環境でまとめて仕事を片付けたいと出勤する人は多いですよね。
仮に土日のいずれかだけ、毎回3時間残業したとします。そうすると月12時間プラスです。仮に土日いつもとなると、月24時間となります(祝日は完全に休んだと仮定する)。
そうすると、先ほどの約80時間に12時間や24時間を足さないといけませんので、100時間前後です。これは7:30~19:30という時計の針が一周したケースでした。
仮に7:30~20:00とすると、4.5/日×約20日+土日の12~24時間=110時間前後となります。過労死イランを大幅にオーバーする水準です。
しかも、これで自宅残業はゼロだった場合です。
お分かりでしょうか?
たしかに今の小中学校にはすごく仕事が多いです。正直、負わされすぎていると思います。そのうえ、放っておくと、国や教委や社会はどんどん学校の仕事を増やす一方です。残念ながら、これまでの歴史がそれを証明しています(そのため、いまの中教審の働き方改革部会では、学校や教員の負担を減らすことを議論しています)。
そんななか、「20時には帰るように」という校長の呼びかけは、理解はできます。せめて20時にはという意味ですし、仕事多い中ありがとうだけど、という意味でもあります。
しかし、上記の簡単な計算でも明らかなように、この水準では過労死してもおかしくない負荷です。悪くとらえれば、本人にその意図は微塵もないのですが、「過労死するくらいの水準で働け」という、ブラックな呼びかけと言われても、反論できないと思います。
このあたりの業務時間と業務量の感覚を校長や教職員はもっておく必要があると思います。
多少残業するときがあっても自然でしょうが、やはり、多くの人が過労死ラインを超えるくらい働ないと回らない、という学校運営は異常です。
19時半や20時以降まで職員室に残っているのは当たり前、という学校も日本中にたくさんあることでしょう。また、「それくらい一生懸命やっているのが教師たるもの当然、よい教師だ」という職場の価値観、学校文化も強いと思います。しかし、それで倒れる人や病気になる人が続出するようでは、ダメですし、みなさん、学校の当たり前に毒されてます。
長時間労働については、国や教委が仕事を増やしている責任も大いにありますが、部活動や学校行事、宿題・テストのチェックなど、学校ごとの裁量、教員ごとの裁量のなかで増やしているものもかなりあります。
※誤解のないように申し添えますが、ぼくは「忙しいのは、先生たち自身のせいだ」と言っているのではありません。が、「学校の経営判断や先生たちの判断で、自ら仕事を増やしてきている部分もあるよね、見直せることもあるよね」と言いたいのです。
「20時には帰ろう」ではなく、「18時には帰ろう」くらいで(それでも2時間の残業ですが。。。)、本腰を入れて大きく見直さないといけないと思います。
★お知らせ 今度かかわっているNPOで学校の働き方改革をテーマに、具体的な取組を立案するフォーラムを開催します。
正直申し上げて、登壇者、参加予定者ともに、すごく多彩でほかでは聞けない話がたくさん出てくると思います。ワークショップもやりますよ~。
※参加申し込みはウェブまたはメールで。

★妹尾の本はAmazon在庫切れが続いておりましたが、復活しました。
多くの方にお読みいただき、ありがとうございます。

思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校―変わる学校、変わらない学校 実践編【I】
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2017/09/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る

変わる学校、変わらない学校―学校マネジメントの成功と失敗の分かれ道
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2015/10/19
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
★参考記事
【忙しい学校 どうする?】小学校教員は専門的でないので定数は少な目、でいいのか?
今日から3連休ですね~。部活の大会とかある方は大変でしょうけど、少しはリフレッシュできそうでしょうか?
食欲の秋。ぼくは、最近すっかりセンブシュー(セブンイレブンのシュークリーム)にハマっており、糖分多めで気を付けないと。徳島県人は甘いもの好きなんですよね~。
↓写真は妻方の父のふるさとからいただいた丹波栗です。めちゃうま。

さて、先日、中教審の働き方改革の部会があって、教員定数(国の標準)の決め方についての話題になりました。小学校はあらゆる教科を教えないといけなくて、1日ほとんど空きコマがない。この配置はなんとかできないか、あるいは教科担任制にできないかという話で。
まずは実態を見てみましょう。教員勤務実態調査2016年実施によれば、週のコマ数は次の分布となっています。ついでに有休取得日のデータもあったので載せておきます。

これを見ると、なんと、小学校では週26コマ以上が4割、21~25も34%もいます。たいして、中学校は担任をもつ、副担任をもつで違いはあるでしょうけど、21~25が5割で、26コマ以上も2割いますね。26コマというと、5時間×4日+6時間×1日ということなので、週で3コマ前後しか空き時間はないということです。その空きコマも休憩ではなく、授業準備、提出物や宿題のチェックとコメント書き、各種事務、場合によっては会議なども入ります。
詳しい議事録は後日公表されると思いますが、文科省の幹部の方(とても熱心ないい方です)の説明の要点として、ぼくが理解したところは次の内容です。
- 小学校も中学校も、基本は学級数に応じて定数が決まる制度となっている。
- 中学校ではより専門性が高い教育が必要ということで、学級数に乗じる計数が小学校と異なる。そのため中学校では教科担任制が敷けるようになっている。
- 教員定数については、教員免許制とも関係してくる。中学校ではその教科の専門の免許。小学校で教科担任制にするとき、この免許制とも絡みも考えていく必要がある。
- これまで学級担任制で長く続けてきた小学校の在り方をどう捉えるかにも関わる話。
詳細はまだ勉強中なので、ぼくの誤解があるかもしれませんが、同じロジックが高校についても言えるようです。高校は週15コマとか、小学校の25コマ以上などと比べてよほど空きコマがある場合が多いです。それはなぜなのか。専門性が高いからということのようです。
要するに、こんなロジックでしょうか?
小学校の先生は、それほど各教科の専門性は要らないよね~
↓
だったら、授業準備も比較的ラクだよね~
↓
だったら、定数上も中学、高校と比べて劣悪でいいよね~
この理屈、どう見てもオカシクないですかーーーー???
いまや道徳や外国語も入ってこようとしています。
9教科や10教科も教えて
(音楽や家庭科は専科の別の先生が教えてくれる場合もあるが、小規模校等ではそれもできない)
+学級活動や学校行事などもやる
+怪我も多いので子どもの給食や掃除、休み時間もしっかり見ておくことが多い
(+地域によっては小学校でも部活動も面倒見る)
これでは、小学校も過労死ラインを超える人が続出するわけだ。
それにどうですか、小学校も明らかに授業準備は時間かかりますよ~。
中学校や高校はひとつ準備すれば、それは5クラスとかに展開できますから、言ってみれば、効率的です。小学校の学級担任制ではそれはできず、毎回、新ネタ披露です。
むしろ小学校の先生のほうが専門性うんぬんは分かりませんけど、授業準備は時間がかかる場合も多いはず。
拙著『「先生が忙しすぎる」をあきらめない』でもいくつかデータを紹介していますが、愛知教育大学等の調査(2015年)によると、仕事の悩みとして「授業の準備をする時間が足りない」と答えた教員は、小学校94.5%、中学校84.4%、高校77.8%です。
もちろん、先生の仕事はやればやるほどという性格はあるので、時間が足りないという回答は多く出る傾向はあると思います。それにしても、この数字は高い。ほぼすべての小学校教員が授業準備の時間が足りないと言っている、というのは異常です。
だって、そうでしょう?
みなさんがかかっているお医者さんが、医学の最新情報を手に入れる暇なんてないよ、とほぼすべての方が言っていたら、この国大丈夫か?って思うでしょう!?
その中教審の場で僕は次の趣旨のコメントをしました。
- 教員定数が教員免許や学校の在り方にも関わる話ということは理解しましたが、2020年度からの学習指導要領はこれまで例をみない大きな改革と聞いています。
- この時期、いまが学校の在り方を含めて、定数の決め方も考える時期ではないでしょうか?
今日はこのへんにしますが、この問題は財源の制約もあるなかで、どうするか、よくよく作戦を練っていきたいと思いますし、問題提起や提案を続けていきます。
※教員定数については次の本をいま読んでおります。とってもわかりやすいです!
★妹尾の本も引き続き応援よろしくお願いします。
★Amazonレビュー、みなさん、お手間ですが、どうぞよろしくお願いします!!!

思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校―変わる学校、変わらない学校 実践編【I】
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2017/09/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
【忙しい学校 どうする?】校長向け研修に労務管理を入れよう
ここのところ、教育委員会や校長会、教頭会、自主的な研究会などにお呼びいただき、全国各地で小中高の管理職向け研修をしています。
地酒(またはワイン)、史跡、海鮮などが好きなものですから、たいていどこの地域に行っても、何かは堪能でき、なんともラッキーです。
テーマは働き方改革、業務改善が最近は多いのですが、組織マネジメント、地域協働、人材マネジメントなども。
教育委員会や校長ら、さまざまな方とお話をしていて、つくづく痛感しているのは、おそらく5年前や10年前と異なり、学校の長時間労働を見直す必要がある、と強く感じている方も多いということです。
長時間労働の問題は、何も今に始まった話ではなく、昔からの話。1950、60年代にもいろんな闘争や議論がありました。その後、給特法の影響もあってか勤務時間の把握などはすっかり下火になった時代が長く続きましたが、最近は再熱、今は風が強く吹いているなと感じます。
先日もある市で、校長や教務主任等を対象にワークショップ型研修をしましたが、部活動の見直し、掃除の時間や朝学習も今のままでいいのか、全国学力テストの試験対策に貴重な3月や4月の授業時間がとられるのは疑問、といった声も、当の校長や教務主任からあがりました。会議の精選などにとどまらず、学校の当たり前を広く見つめなおすことが大事です。ぜひひとつ二つでも、具体的な行動に移していきたいです。

ひとつ、まだ自分も十分できていませんが、管理職等向け研修でぜひやりたいことがあります。
それは、労務管理の知識、情報をもっと入れていくことです。
校長等はとっても人格者で”いい人”が多いです、全国どこでも。さすがに子どもたちを相手に長年教鞭をとられただけはあります。(例外的にパワハラや人権感覚の薄いの人も稀にいますが。。。)
しかし、組織の長としては、”いい人”だけではダメです。とりわけ、労基法の基本をあまり理解していない人や労務管理の必要性の意識がまだまだ低い方もちらほらいます。
教員は長く時間管理になじまない、などとされてきたこともあり、そのレガシー(負の遺産)と言えますが、でも、今日の長時間労働の実態を見ると、そうとばかりも言っていられません。
ぼくは、本『「先生が忙しすぎる」をあきらめない』などを書くとき、いくつか、教員の過労死・過労自殺で公務災害かどうか(=労災かどうか)が争われた事案の判決文や裁定結果を読みました。いまもまだ読み込めていない資料もあり、勉強中です。
このひとつでもよいので、管理職等の研修で一緒に読む時間をつくりたいと思っています。
そうすると、なぜ労働時間の把握が必要なのかが納得できると思います。公務災害かどうか争いが長引いている最も大きな原因のひとつは、労働時間の記録がないためです。タイムカード等で管理されるのはイヤという先生もいますし、どうせ入れても残業代は出ないのだし、過少申告が横行するという方もいます。ですが、ご自身が万一倒れたときのご家族のためにも、正確な時間の記録は必須です。
また、教員の熱心さに甘えて、と言えば言い過ぎかもしれませんが、管理職はたいして業務量の調整とか、相談にのってこなかったのではないでしょうか?ちょっとした声掛けくらいはしたかもしれませんが、多くは先生たちにお任せだった(教員の自主的な裁量での仕事とされてきた)などとばかり言っていられないことも、よーく実感できると思います。
過労死等の事案を読むと、驚くほど共通点があるのです。それは、多くの場合、その教員が相当強い精神的、肉体的負荷のかかる仕事をしていたこと、周りからのサポートがおそらく少なかった(おそらく周りも余裕がなかった)こと、使命感から一人で抱え込んでいた傾向が強いことなどです。
もちろん、マネジメントや業務改善だけで解決できる話ではないかもしれません。教員定数の改善等も急務だと思います。しかし、もっと職場で何とかできなかったのか、悔やんでも悔やみきれないところがあります。
自分の本の宣伝をしたいわけではありませんが、ぼくの本では、過労死等の事案をそれぞれはごく短くですが、報道等された現実を収録しています。「その箇所は本当に読むのがつらかった」という感想を多くの方から聞きました。
そして、多くの教職員が「他人事にはできない、自分の学校で起きてもおかしくない話」、「自分も似たような働き方をしていた」という感想をおっしゃいます。
危機感を変に煽りたいわけではありませんが、学校教育の関係者は、もっと危機感をもっていいと強く感じています。今日はここまでです~。

思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校―変わる学校、変わらない学校 実践編【I】
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2017/09/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
★関連記事
【もうひとつ新刊出ます!】あなたの学校にビジョン、思いはあるか、伝わっているか?
今日は、静岡で御前崎、菊川、掛川の3市の小学校長会、講演やちょっとした情報交換をしてきました。
年間のテーマが不登校、問題行動ということで、その話ばかりはしませんでしたが、組織力ある学校づくりという観点で、
不登校などを表層だけでとらえずに、あるいは担任任せだけにせずに、どのように分析し取り組んでいくかという話をしました。
また、不登校ゼロという目標でいいのだろうか?
それはヘンな登校圧力になっていないだろうか?
結果として不登校がゼロになったらなってでいいことかもしれないが、もっと手前でめざすべきものがあるのではないか、
そもそも校長として、どんな子どもたちの力を高めたいか、明確にして、語っているだろうか?その点に関連して教職員の知恵やアイデアを出しているだろうか?
たとえば、やりぬく力、あきらめない力を高めたいという目標の場合、不登校がちな子の場合、その力はどうなっているだろうか、人と接する機会が極端に減ることでそうした力も弱まっていないだろうか、だとしたら、どうしていけばいいだろうか?
学校の教員だけで頑張っても、とてもしんどいケースも多い。だれとどう連携したらよいだろうか?
そんな問いを立てて、振り返る場としました。正解のある世界ではありませんが、学校が抱えるとても重要なテーマです。

この点とも関連しますが、今度『変わる学校、変わらない学校』の続編が出ます。
いま新刊『先生が忙しすぎるをあきらめない』も多くの方に手に取っていただいていますが(ありがとうございます)、こちらの『思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校』も、とっても気合入れて書いてます!
家で写真とりました。派手な絵は妻の趣味です。。。

まったく自画自賛ですが、とても具体的に、学校づくりを見つめなおし、行動に踏み出せる一冊です。
紹介文として、次のものを書きました。
★★★★★
あなたの学校にビジョンや戦略はあるだろうか?
あったとしても、それは教職員に本当に届き、行動になっているだろうか?
本書では、学校づくりのビジョンと戦略を描き、コミュニケーションし、浸透させていくときのポイントを、ありがちな失敗例をもとに具体的に考える。
学校のグッドプラクティスのみならず、企業等の興味深い知見も紹介しながら、
思いを実現する学校にしていくためのヒントを豊富に解説した。
小中高の管理職はもちろんのこと、教職員、行政職員、保護者や企業等として学校の支援者となる人にとっても、日本の学校を理解し、変えていくための実践的なガイド。
★★★★★
ぜひ手に取ってみてください。学事出版さんに注文いただけるとAmazonよりも早く届きます。リンク先は下記の注文ボタンです↓
思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校:学事出版

思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校―変わる学校、変わらない学校 実践編【I】 (変わる学校、変わらない学校実践編)
- 作者: 妹尾昌俊
- 出版社/メーカー: 学事出版
- 発売日: 2017/09/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
★関連記事


